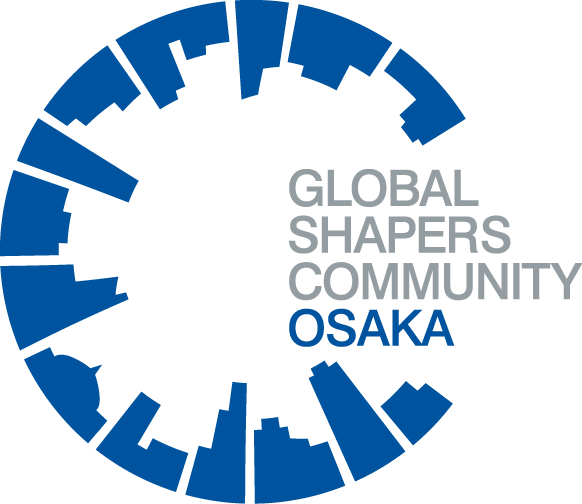大阪・関西万博のパビリオンディレクターが語る「人類の調和」
——かんたんに自己紹介お願いします。
大阪大学で「バーチャルビーイング」という研究をしています。
まず、私たちの意見や行為を代替してくれる、自分らしいエージェントを作ります。それが誰かとネゴシエーションしてくれたり、合意形成をしてくれたり、その結果を持ち帰ってくれたり、そんな存在感を持ったものをつくる研究をしています。
私たちの身体という制約は、人類としてのコミュニケーションや集団として共同に考えることの限界をつくっていたと思うんですけど、新しい身体性で新しいステージに持っていくことはできないだろうか?それに際しての社会的な問題は何かといった観点から研究しています。
——掘り所しかない自己紹介。端的に言うと、クローンみたいな感じですか?
たしかに、デジタルツインみたいなものと近い発想を持っているかもしれません。
ただ、自分とクローン、デジタルツインみたいなものの間で一貫性が保てているのであれば、自分そのものである必要がそのうちなくなると思っています。
——クローンは、自分の分身的な意味合いがありますもんね。だから、同じ属性である必要がなくなるということですね。
自分そっくりの外見や声、意見を表明するものを入り口に、人々がデジタルツインやクローンを使い始めるのは間違いないと思います。
でも、じきにそうでなくてもよくなると思っています。どういう存在感を伴ったものが自分のアイデンティティとの一貫性を持っているのかは、必ずしもドッペルゲンガーみたいなものだけではないかもしれないと思っています。
——素人質問が続くんですけど、物理のロボティクス的に作っているんですか?それともソフトウェア的な、知能や内面的な部分を作っているんですか?
石黒浩先生という、物理的なアンドロイドを作っていらっしゃる方のところで研究しています。
同時に、物理的な身体は必ずしも必要じゃない、それによって考えることができたはずのものが考えられなくなっているという風にも思ったりして。特に、ソフトウェア的な、バーチャルなものにも興味を持つようになりました。
——今は、研究活動がメインですか?
本来は研究と言いたいんですけど、今年は大阪・関西万博が開催されている中で、大阪府と大阪市が出展する大阪ヘルスケアパビリオンで、数年前からディレクターをしています。
また万博で多くのGlobal Shapersが関わっている国際シンポジウム「Shape New World」のプロデュースもさせていただいています。会期中の8日間に分けて、日本人の25人のShaperが中心になって企画して、海外の登壇者と合わせて120人が登壇する24個のセッションを準備させてもらっています。
また、2050年の未来社会の姿を主体的に提案して、そこからバックキャストするという研究にも取り組んでいます。これはフューチャーデザインやスペキュラティブデザイン、SFプロトタイピングとかいろんな分野が重なり合ってできています。以前にはムーンショット型研究開発事業で、現在はJSTのRISTEXと一緒に調査研究を進めています。僕のテーマは、個人と集団の幸福が両立するような未来社会に関する研究に取り組んでおります。
あとは趣味みたいにいろんなプロジェクトをやっています。
——挙げればキリがないくらい、いろんな顔を持っていらっしゃるんですね。
佐久間さんの顔の一つがGlobal Shapersコミュニティだと思うんですが、Shaperになったのは何年前ですか?
たぶん19歳か20歳の時なのですが、見てみます。
——大丈夫ですよ(笑)最初、Shaperになったきっかけとかあるんですか?
Shaperになったのは2018年ですね。だから7年前くらい。
きっかけは、海外留学から帰ってきたことだと思います。その時に大阪ハブにいらした方の何人かと知り合って、参加させていただいたという感じ。
——留学はどちらに?
カナダのトロントと、アメリカのシリコンバレーです。
——シリコンバレーでは、何をされていたんですか?
パナソニックがシリコンバレーに研究所を持っていたので、そこで研究に取り組んでいました。
——そこから帰国して、Shapersに出会ったというわけですね。
Shapersでの7年全てを語るのは難しすぎるかもしれませんが、メインでやっていたことを挙げるなら何がありますか?
今にも繋がっていておもしろいんですが、Shaperになる直前に、Next Dayっていう大きなシンポジウムを開催させていただきました。
今では本当に「社会が変わった」というステージに入ったんですけど、当時はディープラーイングが流行り始めて「社会が変わるかも」と言われていたくらいでした。
その「変わるかも」の時代の中で、AI時代の未来の教育について考えるシンポジウムをやりました。トビタテ!留学JAPANのディレクターだった船橋力さん、世界経済フォーラムのヤング・グローバル・リーダーズ(YGL)にも選ばれたアーティストの草野絵美さん、登録者200万人の阪大理系YouTuberだったはなおさん、人工知能によって経済がどう変わるかといった研究をされていた井上智洋先生、この4人に登壇していただきました。全体を企画させていただいたのでよく覚えています。
その後キュレーターをさせていただいた時には、直井彩茄さんというデザイナーさんとウェブサイトを大きく作り替えさせていただきました。
——各所で聞きますよ、「大阪ハブのLPすごいかっこいい!」と。
私がかねてよりお世話になっていたウェブデザインの会社に頼んで、その会社と直井さんが中心に三者で今のウェブサイトを作りました。
あと、大阪ハブのキャッチコピー「永続的な祝祭」は、私のキュレーターの任期中に当時のメンバーとずっと話し合って作ったものです。今後どれくらい使われるのか、どうアップデートいただけるのかはわからないですけど、今も残っていることは嬉しいです。
みんなで長く議論して決めたものですが、「祝祭」や「永続」は僕が最初に提案したものでもあるので、思い入れもあります。
——それが残っているのはすごいですね。
その時に所属しているみんなで考えていくべきだとは思うんですけど、「思い出に残っていることは何ですか?」と聞かれると、こういうのが思い出ですね。
現在取り組んでいることとしては、Shape New Worldをみなさんとやっているのが、とても印象深いです。
——Shaperとして活動する前と後で、大きく変わったことってあったりしますか?
Shaperのリソースみたいなものって、積極的に使おうとしないとあんまりないんじゃないか、放っといて何か起こるタイプの組織じゃないんじゃないかと思います。
ダボス会議など上が提案してくれるプログラムに自分から応募して参加したりとか、Shaperの方が集まる機会に積極的に参加する方なら違うと思うんですけど。
僕は全国のShaperにたくさん会っていたタイプではなかったですが、お誘いをいただくのは嬉しいです。お互い、何かのプロジェクトの候補者として他の人と並んだ時に、「Shaperという同じコミュニティの人を誘おうかな」と思ってもらえるような緩やかな繋がりがShaperにはありますよね。
あとは……
続きはPodcastにて!
▼佐久間洋司 Hiroshi Sakuma
1996年生まれ。大阪大学ではアバターやエージェントを用いた新しいコミュニケーションの研究に取り組む。2025年大阪・関西万博では大阪パビリオンのディレクターとして「未来のバーチャルビーイング」の展示を統括する。大阪大学と科学技術振興機構の共同研究プロジェクトである未来社会デザインに係る調査研究の研究代表者も務める。大阪商工会議所 未来社会創成委員会 座長、日本SF作家クラブ会員ほか。2021年にはムーンショット型研究開発事業の調査研究でチームリーダーを務めた。2022年に日本オープンイノベーション大賞文部科学大臣賞を受賞。Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023に選出。
▼聞き手
半井翔太 Shota
Curator (25-26), Global Shapers Osaka hub
▼編集
丹下櫻子 Sakurako Tange
Associate member, Global Shapers Osaka hub